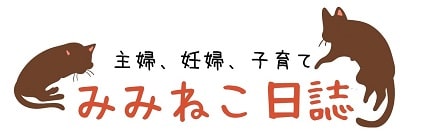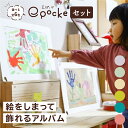保育園や幼稚園、学校で作った作品、おうちで時間をかけて作った作品たち。
すてきな作品たちを見ていると、初めて経験したことやできるようになったことに感動して、全ての作品を残したい気持ちが出てきますよね。
お家の収納スペースというものは限られているので、とりあえず残すという選択を続けているとお家に物があふれてしまいます…。
家族構成やお家の大きさにもよりますが、実際に全ての作品を置いておけるご家庭というのは少ないと思います。

「何もせずに捨ててしまうのは…」と作品をどうしていいか扱いに悩んでしまいます
そんなときに参考にできるよう、さまざまな方法で作品の収納方法・保管方法・破棄する前の思い出の残し方をご紹介させていただきます。
忙しいから、不器用だから簡単なものしかできないという方も自分に合う方法が1つでも見つかれば幸いです。
良かったら少しでも参考にしてみてください。
子どもの作品ってどんなものがある?

子どもの作った作品は色んな思い出が詰まっていて、些細なモノでも残したくなりますよね。
例えば
- はじめてのお絵かきやハサミを使ったなど思い出の作品
- 保育園や幼稚園、学校で作った作品
- 書いてくれたお手紙
- 足形や手形などの記念
- クリスマスや子どもの日など、イベントに関係した作品
などがあります。

もっと細かいものだと、毎日保育園で作った折り紙、ぬりえなど挙げていくと本当に大量になってきますね。
3つの方法
作品をどうするのか、主に4つ挙げられます
- 飾る
- リメイク
- 収納
- 捨てる
それぞれでおすすめの方法を紹介していきます。
飾る
壁にそのまま貼る

マスキングテープや壁紙に貼れる両面テープを使用することで、簡単に傷つけずに壁に飾ることができます。
また賃貸でも画びょう使用可能なところもあるので、確認してみてください

何度も同じところを差したりすることで大きい穴があいてしまわないように注意が必要です
額縁入れて飾る
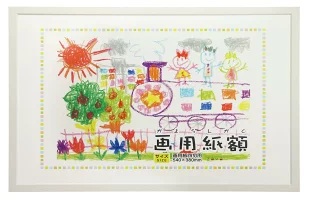

額縁を使うことで綺麗に作品を飾ることができます。
飾る作品の色味をそろえたり、飾り方を工夫することで、お部屋のおしゃれなインテリアとして飾れます
立体的な作品は飾る場所を決めて飾る

立体的な作品については、主にキッチンカウンターやおもちゃ置き場の棚、玄関など飾るエリアをあらかじめ決めておくことで部屋が散らかっている雰囲気がなくなり、インテリア感覚で飾ることができます
季節やイベントに関連した作品は都度持って帰ってくることが多いので、飾ると部屋に季節感が出てきてより作品を楽しむことができますね。

作品を入れ替える際に季節や時系列で分けて作品を保管しておくと、もう一度飾りたい場合に取り出しも簡単になります。
飾る作品を決める時は

飾る作品は子どもと相談しながら決めると、コミュニケーションの時間を楽しみつつ、子ども自身が上手くできたと思う作品を認めてもらう実感を得て、自信にもつながります。
リメイク

作品を日常で見ていたい方はリメイクがおすすめです。
他の方法と比べると時間はかかりますが、日用品として使ったりコンパクトに収納できるので子どもも嬉しくなりますね。
リメイクものとしては以下のように色々あります。
- しおり
- トートバッグ
- Tシャツ
- 絵本
- フォトブック
- シール(ステッカー)
料金はかかりますが、データを送ってオリジナルの商品を作ってもらったり、100均グッズを利用して、自作することができます。
収納方法
捨てたくない作品は収納して残しておいておきたいですよね。
1歳2歳の頃は全て残していても大丈夫ですが、どんどん量が増えてきてしまいます。
収納する前に残すルールや収納グッズを決めておくと、お片付けの時間がスムーズになります。
作品を子どものために残すのか、親が見たいから残すのかを考慮するとルールが決まりやすいかもしれません。
例えば
- 毎日持って帰ってくるぬりえや折り紙は捨てる
- 子どもが何を書いたか覚えていない場合は捨てる
- 季節ものは必ず残しておく
- 平面のものは残して立体の作品は写真だけ残す
など、自分で残す基準を作っておくことが大事です。
季節ものなど都度持って帰ってくる作品もありますが、年度末や長期休みの前に大量に持って帰ってくることが多いです。
そのタイミングで現在収納しているものと合わせて作品を収納するか捨てるかを選びます。
どんな収納グッズを選ぶべきか
収納ボックスや収納グッズを用意しておくと、大きさが決まっているので際限なく残すことがなくなります。
沢山残したい方はコンテナタイプに立体的な作品と、絵などの平面な作品を小分けの収納ボックスに入れてから一緒にまとめて収納しておくと1箇所にまとめて作品を置くことができます。
残す作品の量や部屋の収納ペースに応じてケースを決めていきましょう。
収納作業を続けることが苦手な場合
作業が多くなるアルバム式の収納グッズを購入するのではなく、入れるだけですむボックスがおすすめです。
追加・変更がしやすいように、最初は無印や100均など安価な収納ケースでの収納がおすすめです。
長い間保管していると何を作ったのか忘れてしまうため、手間でなければ何を作ったのか、どういう気持ちで描いたのか子どもに聞いて年齢や日付と一緒に付箋やメモで残しておくとおすすめです。

子どもの人数が複数の場合は名前も書いておくと分かりやすいですよ!
将来
子どもが大きくなって作品に興味がなくなり、全て不要だということがあるかもしれません。
その時は子どもが成長したと感じて、親が要るもの以外は捨ててしまってもいいかもしれませんね。
年度末で作品や足形を並べて子どもを一緒に記念撮影をして写真を残しておくと、一年の最後のイベントとして子どもも楽しめますし、成長記録も作ることができますよ。
捨てる

捨てる作品に関してできるだけ事前に子どもに「バイバイしてもいい?」と確認をとってから捨てた方が望ましいですが確認すると全部置いておきたいという子もいますよね。
その場合は作品を収納場所とは別の場所に一旦おいておき、期間を置いて子どもが何も言ってこなければ捨てるといったワンクッションおいておくと、子どもが「作った○○どこ?」と聞かれても出すことができます。
捨てる前に写真を撮るのもおすすめ
捨てる前に1つ1つ写真に残すことで、作品自体を残さずとも思い出として残すことができます。
絵であればスキャンしてデータを置いておくのも1つの手ですね。
写真を印刷してアルバムに残しておくこともできるし、データのみ管理して「みてね」アプリなどで共有することもできます。
データで管理する場合はPCなどフォルダでまとめて保存しておくと、後で印刷したいときやリメイクで使用したい場合に便利です。
写真を印刷する際は毎月無料で印刷(送料別)できる「ALBUS」や「しまうまプリント」などのアプリもあるので活用するのがおすすめです。

ALBUSは毎月8枚無料ですが「T3B8Z」の招待コードを使用すると毎月9枚無料になります。